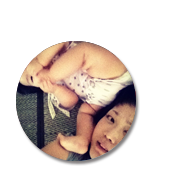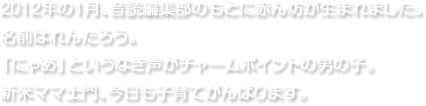「あなた」2019.8.10

つい先日、台所でお皿を洗っていたら、廉太郎に「携帯の番号教えて」と言われた。
「誰の?」と聞くと「あなたの」と言う。
「あなた」と言われて驚いたけれど、言われるがままに携帯電話の番号を教えた。廉太郎はたわむれに電卓にその番号を打ち込み、「最初に0がつけられへん」とぶつくさ言っている。「あなた」と言われたのは初めてだなあと思いながら、お皿洗いに戻った。
高校生の頃、国語の先生に「親のことを二人称で呼んだことがある人」と聞かれ、手を挙げたことがある。
確かそのとき、わたし以外にはほとんど誰も手を挙げていなくて、そのことにすごく驚いた。
「土門が初めて二人称で呼んだのはいつ?」と聞かれ、「小学生の頃です」と答えると、「それは早いねえ」と先生は笑った。
「子供が親を『お母さん』『お父さん』ではなく、二人称で呼び始めるときというのは、親をひとりの対等な人間として見なし始めたときだそうよ」
だから高校生にもなってまだ二人称で呼んだことがない人は、親離れができていないのかもね。そう言って、先生はまた笑った。
母のことを「あなた」と呼んだのは、小学2年生くらいのときだったと思う。
母に「片付けをしろ」と言われて、「あなただってしてないじゃん」と答えたのだ。間違って「あんた」と聞こえてしまわないように、細心の注意を払って言った「あなた」という言葉だったが、それを聞いた母は烈火の如く怒ってわたしを叩いた。あんなに怒ったのは、それまでにもそれからもなかったから、わたしはその日のことを結構鮮明に覚えている。
「えらそうに」とそのとき母は言った。「あなたという言葉のどこがえらそうなん?」と口答えすると、もう一度叩かれそうになったので慌てて逃げた。
あのときはまったくもって理解できなかった。「あんた」でも「お前」でもない「あなた」という言葉が、どうしてあんなに母の逆鱗に触れたのか。
高校生になってから国語の先生の話を聞いて、「ああ、そういうことだったのか」と思った。母は、わたしに対等に見られたことがいやだったのだ。
奇しくも廉太郎がわたしを初めて「あなた」と呼んだのも、同じ小学2年生だった。
だけどわたしは怒りもせず驚いてみせたりもせずに、彼の「あなた」をそのまま聞き流した。もしも口答えで「あなた」と言われていたら怒っていたかもしれないから、このタイミングで言ってくれてよかったなと思った。
最近思うのは、わたしは廉太郎を怒りすぎているということだ。物を出したら散らかしっぱなし(この点はわたしと似ているのかもしれない)、口を開けば「あのおもちゃ欲しい」「このおもちゃ欲しい」だし、宿題は言わないとしないし、いつもテレビの前を陣取っている。
そのたびに怒りながら、「どうしてわたしはこの子を怒ってしまうんだろう?」ということを考えていた。人の子だったら怒らないのに。
そう思った瞬間、そうか!と閃いた。
そうか、わたしはこの子を自分の子だと思っているんだ。つまり、「自分のもの」だと。だから思い通りにいかないと怒るんだ。
「あなた」と言われて、なんだか頭が冷やされる思いだった。
廉太郎はわたしのものでもなんでもない。わたしはただ世話をしているだけで、彼の人生は彼だけのものだ。彼にとって確かにわたしは「お母さん」ではあるけれど、「あなた」と呼ばれた瞬間、簡単に他の誰かと同じ立ち位置になる。つまり「自分以外の誰か」という立ち位置に。「あなた」という言葉は、親密なはずなのにどこまでも平行線で決して重なることがない、切なくて不思議な言葉だと思う。
廉太郎とわたしは、どんどん離れていっている。昔は体ごとひっついてしまっているんじゃないかと思うくらいずっと一緒にいたのに、今では手が触れることすら照れ臭い。それなのにわたしの気持ちだけがまだ離れていなくって、それでわたしは苛立っているんだろう。
今度わたしも廉太郎を「あなた」と呼んでみよう。間違って「あんた」と聞こえてしまわないように、細心の注意を払って。そのとき彼はどんな顔をするだろう。わたしはどんな気持ちになるだろう。
ちょっと寂しい気持ちになるかもしれない。だけどそれは、今よりもずっと良いことのはずだ。