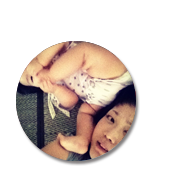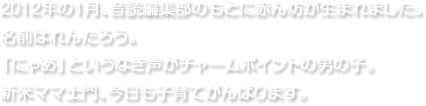水泳教室を辞めた日2019.12.10

廉太郎が、1年間通っていた水泳教室を辞めた。
水泳教室は、彼が小学校に上がるのを機に、何か習い事をさせたいと思って始めさせた。わたし自身出不精で、休日にはずっと家で書いたり読んだりしてばかりいるから、子供と外で体を動かしたり、新しいことを教えたりというのが得意ではない。だけど家でテレビを観ているくらいなら、外に出てプロの大人から何かを教えてもらったほうがいいのではないかと思い、習い事をさせることにしたのだった。わたし自身は幼いころ習い事をしていなかったので、コンプレックスもあったのだと思う。
それで町内のお祭りのときに、近所の賢そうな高校生をつかまえて「やっててよかったと思う習い事は何か」と尋ねた。どうせなら、若い子の意見を参考にしようと思ったのだ。すると「水泳」だと言う。基礎体力がつき、運動が得意になるのだと。それで、すぐに水泳教室に通わせ始めた。廉太郎も最初は乗り気だった。水に入るのは楽しい、ということも言っていた。でも日が経つにつれて、次第に行きたがらなくなっていった。
理由はひたすら「先生が怖い」「だから楽しくない」というものだ。
以前も書いたが、いつも髪を切ってくれている美容師さんにその話をしたら、すぐに辞めさせるべきだと言われた。
「だって実力や友人関係は自分でどうにかできるかもしれないけど、先生は選べないじゃないですか。それって拷問みたいなものですよ」
彼の言葉を聞いたとき、本当にそうだなあと思った。
それで怖い先生がいない時間帯を割り出して、その時間に行くようにもしたのだけど、どうやらもう、廉太郎は水泳教室全体の雰囲気がだめみたいで、休むことが続いていた。「行きたくない」「行きたくない」とさめざめと泣き、玄関でうずくまるのだ。朔太郎が「ないてるー」と言い、わたしの顔を見る。廉太郎はわたしが「もう休んでいいよ」と言うまで、ずっと泣き続けるのだった。
そんなある日、廉太郎が通う学童で秋祭りがあった。
焼きそばを売りながら、他のお母さんたちに「習いごとって何させてます?」と聞いてみた。すると両方のお母さんが「水泳」とおっしゃった。しかもうちと同じ水泳教室だ。大きいのですれ違ったこともなくて、「同じところに通ってるんですね!」とびっくりしたりした。「みんな通っているんですね」「あそこは有名ですからね」
彼女たちの子供が焼きそばを買いに来た。ふたりとも、廉太郎の級友だ。それでこっそり、彼らのお母さんに聞こえないように「水泳楽しい?」と聞いてみた。
ひとりの男の子は「全然」と言い、もうひとりの男の子は「早く辞めたい」と言った。ふたりとも即答だった。
わたしは少し驚いて、重ねて尋ねる。「どうして辞めたいの?」
するとひとりの男の子はこう言った。
「だってしょうもないんやもん」
しょうもない! わたしは衝撃を受け、彼の顔をまじまじと眺めた。
「それは、教え方が下手ってこと?」
「いや、下手かどうかはようわからんけど、なんか、ぜんっぜんおもんないねん」
彼は苦々しそうに続ける。
「はよ辞めたい。でも、お母さんが辞めさせてくれへんから、しかたなく行ってる」
そうかあ、とわたしはため息をついた。この子も、廉太郎と同じようなことを感じているのだ。
「廉太郎も、辞めたいって言ってるんだよね」と言うと、彼はそっけなく「そらそやろ」と言い、
「え。れんたろう、やめんの?」
と尋ねてきた。
「うん、多分」
「えー、ええなあ」
彼は、とても羨ましそうに言った。
わたしは、廉太郎の級友の男の子と話しながら「気の毒だな」と思っていた。
行きたくないのに行かされて、しょうもないとかおもんないとか思いながら泳いでて。
遠くで廉太郎が、友達とおもちゃで遊んでいる。廉太郎が楽しそうに笑っているのを見ながら、「だけど、わたしはどうして、他の子供の言うことだったらこんなに簡単に信じられるんだろうな」と思った。
わたしは廉太郎の言うことを、今みたいにすぐ信じることができなかった。
それはあなたが怠け者だから、臆病だから、根性が足りないから。
そう思ったし、そう言っていた。あれだけ泣いて訴えられても、原因を全部、廉太郎のほうに見出そうとしていたのだ。
廉太郎が手を振ってくる。「おかあさーん、お金がないー」と大きな声で言って。
わたしは手を振り返しながら、内心とても反省していた。そして、水泳教室を辞めさせることを決意したのだった。
次の水泳教室のとき「もうプール辞めていいよ」と言うと、廉太郎は「うそ!?」とすごく驚いた顔をした。
「ほんまに辞めていいの!? ほんまに!?」
嬉しそうに叫ぶ彼を見ながら、そんなに嫌だったのかと思う。
「がんばって通わせたんだけどなあ」と惜しい気持ちが湧く一方で、「これは損切りだ」と自分に言い聞かせた。
何かで読んだことがあるが、ギャンブルの泥沼というのは、それまでの投資を取り戻そうとするところから始まるらしい。それで結局、増やそうとしたのに逆に借金を作ってしまう。
廉太郎の習い事の件も、それと同じなんだろうと思った。好きになってもらおうとしたのに逆に嫌いになってしまっては、大損もいいところだ。意味のない投資は、もう今日で終わりにしよう。
その日、水泳教室が終わったあと、ふたりで受付へ行き、退会届けをもらって机の上で記入した。
名前と住所を書いて、退会理由のところまで来たところで、なんて答えるべきなのかふたりでこそこそと話し合う。
「『不満』っていうのがいちばん妥当だけど、なんか、丸しにくいよね」
「うん、『ふまん』は、ちょっといやな感じやな。もっとええのないの?」
「『家庭の都合』にしようか」
「そうやな、それにしよう」
気の小さなふたりで腐心したわりには、その退会届けはほとんど目を通されずに受付のお姉さんに処理された。
「はい、では11月末までで」
おつかれさまも、ありがとうもなく、下を向いたまま言われる。
わたしたちは拍子抜けして、そそくさと出口へと向かっていった。
あたりはもうとっぷり日が暮れている。
しらじらと灯がついた館を出ながらようやく、「ああ、わたしもここが本当は好きじゃなかったんだよな」と思った。
きいきいなる回転椅子も、穴のあいたソファも、古い空調も、靴を入れるボロボロのビニル袋も、ばたばたと騒がしい更衣室も。
本当は全然好きじゃなくて、全然来たくなかった。そんなことに、今更気づいたのだった。
「ママもここ、ほんとは好きじゃなかった」
自転車を漕ぎながらそう言うと、廉太郎は「そやろ?」と言う。
わたしは自分の感覚すら信じられてなかった。廉太郎が楽しいかどうか、わたしがここを好きかどうか、ちゃんと見ることができていなかった。
有名だから、すすめられたから、みんな行ってるから、そっちのほうばっかり信じてしまって。
「辞めれてよかった。すっきりした」
廉太郎は、冷たい風に濡れた髪の毛をさらしながら、清々しい顔をしている。
「他に何かやりたいことあるの?」と聞くと、「なんもしたくない」と言った。
その声があまりに嬉しそうだったので、「今度は、廉太郎がやりたいことを見つけるまで待ってみよう」と思った。
自転車を漕ぎながら、もうここに来ることはないんだなと思う。
「よくがんばったよ、廉太郎は」
そう言うと廉太郎は「あんまりがんばれんかった」と言った。
1年間通った道を、ふたりでゆっくり帰っていった。