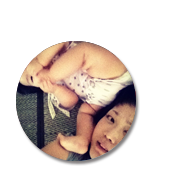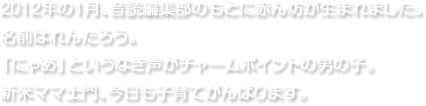兄弟の「優しい世界」2019.6.10

わたしはひとりっ子なので、兄弟のいる感じというのがよくわからない。
家にあるおもちゃも食べものも洋服も、両親の愛情も視線も、全部独り占め。
兄弟と比べられることもないし、兄や姉に煙たがられることも、妹や弟に合わせることもない。けんかをすることも、仲直りすることもない。
マイペースに、自分本位に、これまで生きてきたように思う。そしてそれで特に問題がなかった。
そんな自分がふたりのこどもを産んだ。ふたりは「兄弟」となった。
だけどわたしには「兄弟」の感じがわからないので、ついデリカシーのないことをやらかしてしまい、知らず知らずのうちに彼らを傷つけていることがあるんじゃないかと思っている。でも、ひとりっ子だからこそ、「自分がこんなこと言われたりされたりしたらたまったもんじゃない」というのは、人一倍思うかもしれない、ということも思っている。
たとえば「お兄ちゃんなんだから我慢しなさい」とか。
わたしだったら言われている意味がわからないと思う。「生まれた順番云々ではなく、個人対個人の話だろう」と思う。
だから、言わない。朔太郎が廉太郎のおもちゃを欲しがっていたら、朔太郎に対し「『にいに貸して』と言いなさい」と言う。
廉太郎には「今貸すのがいやなら、『あとで貸すからちょっと待って』と言いなさい」と言う。とにかくふたりで話し合って決めろと言うのだ。
廉太郎は「朔太郎はまだ小さいんだから、そんなこと言ってもわからないよ」と困った顔をし、結局、朔太郎に貸してあげている。いい子だと思う。
たとえば「ひとりで食べないで、仲良く分けて食べなさい」とか。
わたしは胃腸が弱いくせに食い意地が張っている。それはひとえに自分がひとりっ子だったからだと思っていて、自分の好きな食べ物は、自分の求める分量だけ食べたいという気持ちがとても強い。だから、「仲良く分けて」などもってのほかなのだ。世の中には「仲良く分け」ることが目的である食べ物と、そうではない食べ物が存在する。後者に関して言えば、他人が何をどれだけ食べようと勝手だが、わたしの食べ物には手を出さないでいただきたい。
だから、言わない。だけど、廉太郎がアイスを食べていて、朔太郎がそれを「くれ」と言って泣き出したら、「あげなさい」と言う。
「朔太郎の目の前で食べるあなたが悪い。それは『くれ』と言われるに決まっているだろう。ひとりで全部食べたいなら、朔太郎から隠れて食べなさい」
廉太郎は「はあい」と言い、居間のすみで隠れて食べる。でも朔太郎はどこにでも歩いてついていくので、すぐに見つかる。それで仕方なくほんのちょっと分けてやっているのだけど、分けると「これはうまい」と朔太郎に気づかれてしまうから、結局たくさん横取りされている。
たとえば「(弟に向かって)お兄ちゃんはおかしいねえ」とか。
集団というのは簡単に暴力性を帯びる。たとえばお兄ちゃんが何かしょうもないことをした際、「お兄ちゃんはだめだねえ」「おかしいよねえ」と弟や妹に同意を求める構図というのが存在するけれど、わたしがもしこれをされたら悔しくて悔しくて癇癪を起こすと思う。こんなの仲間はずれじゃないか。
だから、言わない。「廉太郎はおかしい」と自分が思うのなら、自分ひとりで言う。「お母さんのほうがおかしい」と思うのなら、そう言ってもらったらいい。そこでようやく「よし、やるか」となる。けんかは1対1でするに限る。
世のひとりっ子が全員そうだとは言わない。
だけど、わたしに関して言えばかなり個人主義に仕上がったように思う。
「よそはよそ」「うちはうち」感がかなり強い。それが崩れると、自分が崩壊すると思っているからかもしれない。それが子育てにも出ている。
だけど、なんだか最近、兄弟っていいなと思えてきた。
廉太郎がしかたなくおもちゃを貸してあげる感じ、朔太郎がそれにきちんと甘えて嬉しそうに笑う感じ。それでいて朔太郎は、ちゃんと遠慮もしている。それがお兄ちゃんのものであり、自分は貸してもらっているに過ぎないのだと理解している。
廉太郎は自然と朔太郎に合わせて遊んであげるし、朔太郎はそんなお兄ちゃんが大好きだという顔でまとわりつく。
へえ、そういう世界があるんだな、と思う。わたしが「そうしろ」と言わなくても、彼らは自然とそうしている。
そこには「優しい世界」ができあがっている。
自分を少し溶かしてあげて、分けてあげる感じっていうんだろうか。
理屈の通っていないことも、ちゃんと呑み込んで受け入れる感じ。
「だって僕はお兄ちゃんなんだから」「だって僕は弟なんだから」
それが自然とできるのは本当に素晴らしく、わたしにはないものだと思う。
ひとりっ子の世界が「優しくない世界」とは言わないけれど、自分をかこむ殻がかっちりとできあがっている感じではあった。
わたしはその殻から意思をもって出たり入ったりする。言葉をもってコミュニケーションしようとする。
なぜなら、自分を溶かすことが自然とできないから。自分は自分である、ということを頑なに守ろうとするから。
それがときどき「優しくない」ことを、わたしは自覚している。
「ねえ、廉太郎、アイス一口ちょうだい」
わたしがそう言うと、廉太郎は「えーっ」と言う。
「いやだなぁ」とぶつぶつ言いながらも、必ず廉太郎は一口くれる。いやなら断ればいいのに、と不思議に思うわたしは「優しくない世界」にいる。
廉太郎は、わたしが冷凍庫に入れているアイスや、冷蔵庫に入れているプリンを絶対に食べない。それを勝手に食べると、わたしがものすごく嫌がることを知っているからだ。アイスやプリンを食べられたという事実ではなく、わたしが「殻」を侵食されることを何より嫌がるということを知っている。
ある日、廉太郎が言った。
「お母さんはよく怒るけど、むずかしく怒らないから、こわくない。簡単なことしか僕に言わないから」
ああ、すごいなと思った。ちゃんと見ている。
わたしが、「これはこういう理由で嫌だから、してほしくない」ということを言葉で一所懸命伝えて、「殻」を守ろうとしているのをちゃんと見ている。そしてそれを尊重しようとしている。自分を溶かして。
そんな彼はやっぱり「優しい世界」にいるように思う。
それがときどき、とても眩しく、とても羨ましい。